「自社でBCPを策定したいけど、どうやって策定すればいいのかわからない」と初めてのBCP策定で困っている企業担当者は多いでしょう。
BCP策定には中小企業庁が用意しているガイドラインが役立ちます。
自社のみで策定したBCPは、内容が不十分で効果が期待できないこともあります。
この記事では、中小企業庁が用意している『事業継続計画策定ガイドライン』をもとに、自社でBCP策定をおこなうポイントについて紹介します。
どのようにBCP策定すればいいのかわからない、もしくは策定しているBCPを見直したい方は最後までお読みください。
事業継続計画策定ガイドラインとは

事業継続計画策定ガイドラインとは、中小企業庁が公表しているBCP策定の教科書のようなものです。
近年、地震や火災、爆発、大規模システム障害などが相次いでいます。
一部の企業では、中核となる事業を停止に追い込まれる場合があります。
特に大規模災害が発生すると、事業の継続自体が困難になってしまうことも。
事業継続のため、計画書の作成は必須といえます。
しかし予備知識なしに、一からBCPを策定することは難しいのです。
事業継続計画策定ガイドラインを活用してBCP策定するほうが進めやすくなります。
そうして用意されているのが事業継続計画策定ガイドラインです。
BCPを策定する目的は「事業の継続」
BCPを策定するのは大事だと理解する一方、BCPの目的がわからない方もいるでしょう。
BCP策定をする目的は、事業の継続です。
例えば、自然災害や事故、テロといった緊急事態が起こる可能性があります。
そうした場合でも、事業の継続・早期復旧を目指すことが目的です。
事業の継続、もしくは早期復旧を目指すための計画をBCPと呼びます。
BCPの役割は「社会的使命を果たすこと」
BCPの役割は、社会的使命を果たすことです。
企業が事業をおこなうことは、社会的貢献を意味します。
例えば製造業の場合、自社で製造した商品によって、消費者の生活を楽にします。
食品産業の場合、安定的な供給をおこなうことで、消費者に健康的な食生活を提供する役割を担っているでしょう。
しかし緊急事態が発生し、これらの事業の継続が困難になれば、社会的使命が果たせなくなります。
企業が事業の継続・早期発見を目指すことは「社会的使命を果たす」ことそのものです。
事業継続計画のひな形は中小企業庁が用意
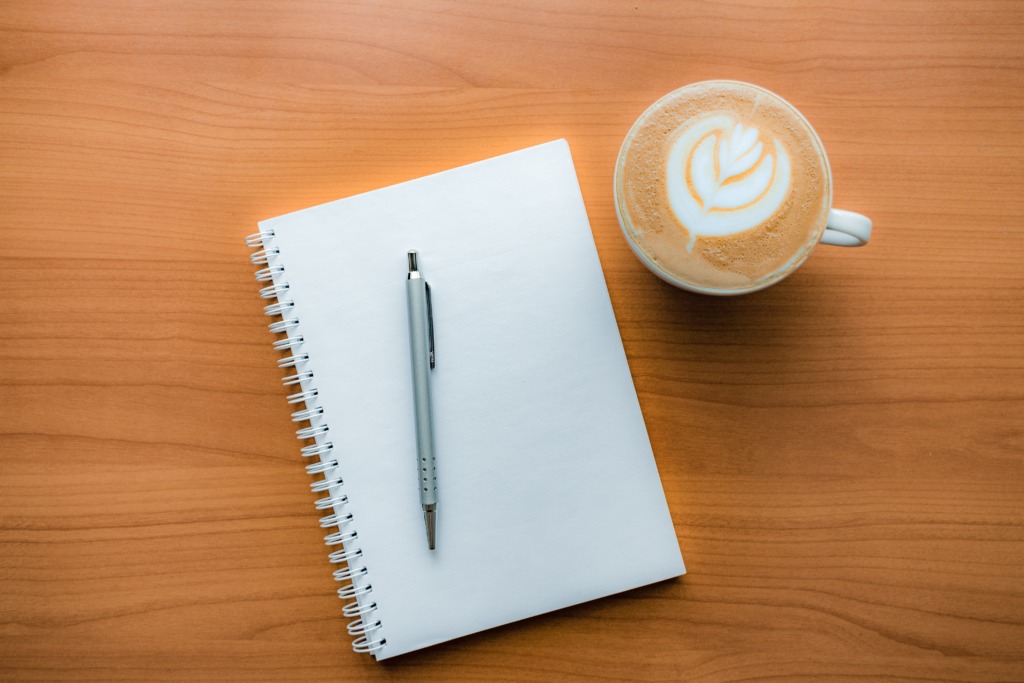
BCP策定にあたり、事業継続計画書を作成することがおすすめです。
文書として記録することで、万が一の緊急事態にも対応できるためです。
口頭のみの事業継続計画では、緊急事態発生時の運用ができません。
また策定した事業継続計画を時代に合わせたものに見直すことも難しいのです。
とはいえ、予備知識なしに事業継続計画書を作成するのは難しいでしょう。
そうした場合のため、中小企業庁が事業継続計画のひな形を用意しています。
以下のURLからダウンロードできますので、ひな形に沿って事業継続計画を作成しましょう。
参照:https://www.chusho.meti.go.jp/BCP/contents/BCPgl_download.html
BCP策定手順の大きな流れを解説
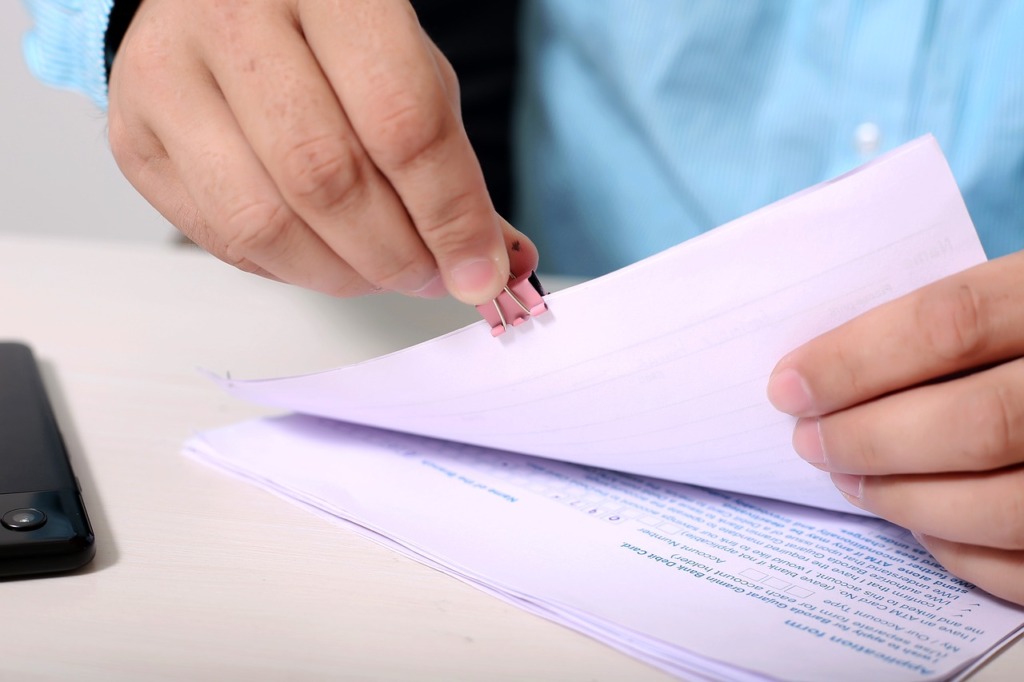
BCP策定の手順は、次のとおりです。
- 対象事業・対象施設の範囲を決める
- ビジネスインパクト分析をおこなう
- リスク分析をおこなう
- 発動基準を明確にする
- 予算を決定しBCP策定する
詳細な策定手順は「BCP 策定 手順」で解説しています。
ここではBCP策定におけるポイントを中心に紹介します。
対象事業・対象施設の範囲を決める
BCP策定するとき、まずはBCPの対象範囲を決めましょう。
企業によって優先するべき対象が異なるためです。
基本的にはすべての事業・業務・施設・人員がBCPの対象です。
しかし企業のリソースや資源によっては、対象を限定せざるを得ないでしょう。
- 中核事業のみ
- 施設に優先順位をつける
- 従業員を最優先する
例えば製造業だと、商品製造のため工場の早期復旧が優先されるでしょう。
このように自社の状況に応じて、BCPの対象範囲を決定します。
ビジネスインパクト分析をおこなう
BCPの対象範囲を決めたら、ビジネスインパクト分析をおこないます。
その理由は、BCP発動基準を決めるためです。
ビジネスインパクト分析とは、企業における事業・業務・プロセス・これらに関わるリソースを把握し、事業継続におよぼす影響の分析をおこなうものです。
ビジネスインパクト分析は、次の3つが目的です。
- 事業継続・復旧の優先順位付け
- ボトルネックの特定
- 目標復旧時間(RTO)の設定
業務を以下の画像のように細分化して分析するとわかりやすいでしょう。
よろしければ参考にしてください。
リスク分析をおこなう
ビジネスインパクト分析の過程において、リスク分析もおこないます。
BCPを発動させる可能性のあるリスクを把握するためです。
リスクマネジメントにおいても、リスク分析と評価は重要です。
どのようなリスクがあるのか、把握できれば対策できます。
洗い出されたリスクの脅威と発生する可能性について、次のような利用可能データを収集します。
- 統計データ
- 新聞の記事
- 過去のトラブル報告
これらのデータを参考にして、BCP発動にいたるリスクを関係者で検討しましょう。
発動基準を明確にする
事業と業務への影響度・目標復旧時間を設定したら、発動基準を決めましょう。
BCPの発動基準がわからないと、事業継続・早期復旧が遅れてしまいます。
緊急事態に直面しても、BCPが発動したのかわからなければBCP策定の意味がありません。
事業継続・早期復旧のための計画を立てていても、いつまで経っても実行されないのです。
BCP発動基準を明確にし、BCPに則った行動ができる体制を整えることが重要です。
予算を決定しBCP策定する
BCP策定のため予算を決定しましょう。
事業継続計画を実行に移すためには、対策の導入や教育といった事前準備が不可欠です。
ビジネスインパクト分析により明らかになった課題を社内で共有しましょう。
そして、復旧優先度や目標復旧時間を意識した機能をもつ設備や備品を採用します。
BCP発動基準に達した際の行動を、社員に教育するための時間と費用も必要です。
いくらBCPを策定しても、実行に移せなければ効果を発揮できません。
自社のBCPの目的を周知させるためにも、各社員の立場・責任に応じた教育と訓練をおこないましょう。
BCPマニュアル作成は事業継続において重要な業務
今回は自社でBCP策定をおこなうポイントについて説明しました。
自社のみでBCP策定をおこなうのは難しいでしょう。
しかしそんな企業のため、中小企業庁では事業継続計画策定ガイドラインを用意しています。
BCP策定の教科書のようなもので、ガイドラインに沿って進めればBCP策定がスムーズにおこなえるでしょう。
BCP策定する目的は、事業の継続です。
また企業は社会的使命を果たすためにも、BCPを策定するべきでしょう。
自社内で効果的なBCPマニュアルを作成するため、事業継続計画策定ガイドラインを有効活用しましょう。

コメント